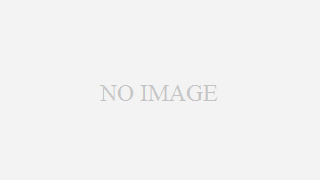 健康増進
健康増進 コースクリエーターのための極上健康法3
体重や外見を気にして食べ物を制限することはありませんか?確かにカロリーを控えることも大切ですが、そのことで脳や体の機能維持に欠かせないタンパク質が不足するリスクがあります。タンパク質不足は、外見の老化、脳や体の機能低下の恐れがあるのです。 ...
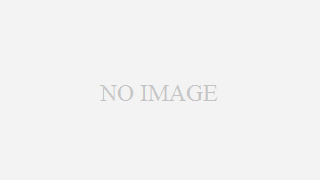 健康増進
健康増進 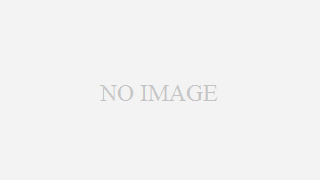 健康増進
健康増進 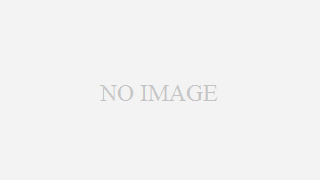 健康増進
健康増進 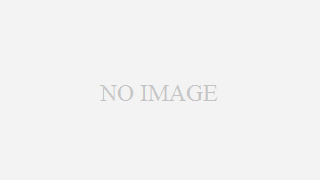 健康増進
健康増進 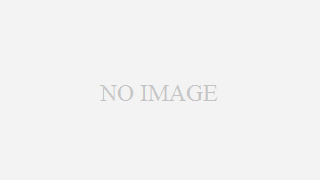 健康増進
健康増進